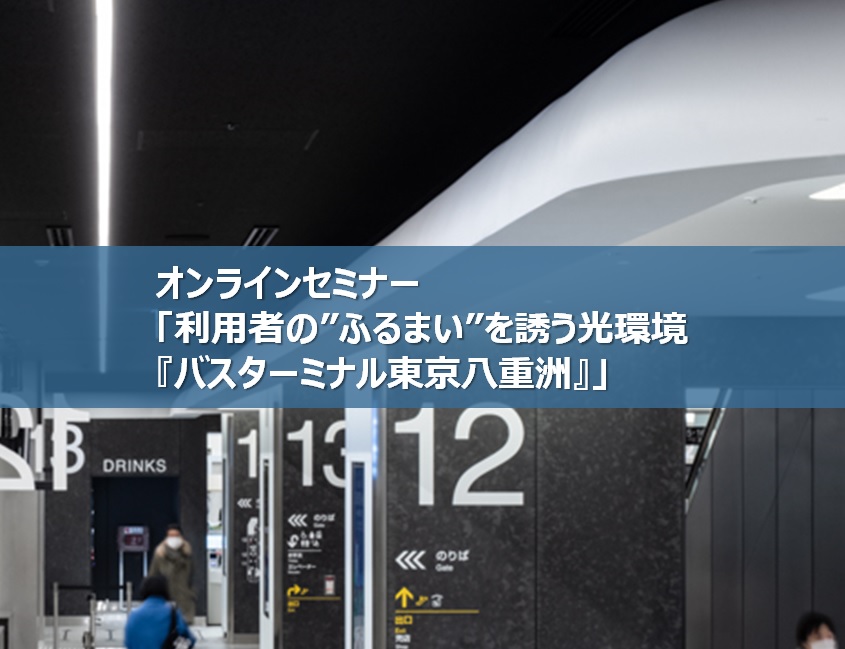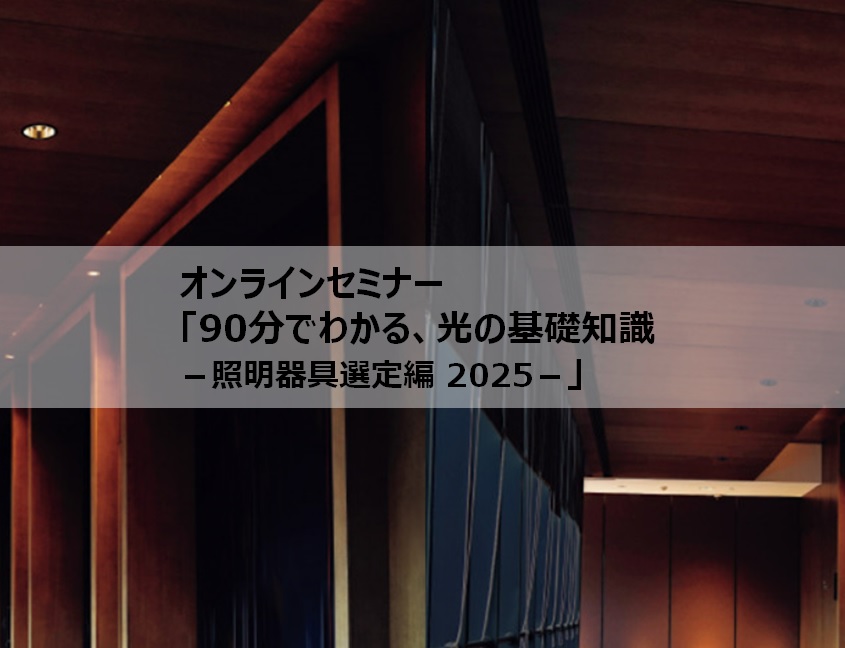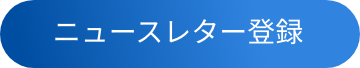インテリアデザインにとって色彩は、空間の印象を操作するだけに留まらず、見る人の心理にも影響を与える重要な存在だ。内装材に色を差すことは多々あるが、赤のカラーライティングで空間を照らしている飲食店の事例を紹介したい。千葉県にある「ひいろ」は、照明によって朱に染まった空間を通して、非日常やシズル感が全身に伝わってくる。設計した八柳有子さん(cotto)に、ライティングに色を用いた理由と工夫を聞いた。
赤い照明とマテリアルが織り成す 非日常の会員制レストラン
「ひいろ」は、JR千葉駅から程近くに建つ複合施設「the RECORDS」の最上階に位置する。ここは、千葉市を中心に平屋の分譲事業などを手掛ける拓匠開発が、築36年の旧ビジネスホテルをコンバージョンした建物であり、地域に開き、隣接する公園とのつながりを生み出すことを目指した施設だ。1階、2階はカフェやベーカリーなどオープンな雰囲気の飲食店が入り、3階と4階には同社のオフィスが入居する。
最上階にあるのが「ひいろ」だ。会員制としているため、セキュリティを設けた専用エントランスからエレベーターで5階に上がると、緋色ののれんが客を迎え入れる。同店は、事業主である拓匠開発が、千葉エリアにビジネス面での交流の場が少なかった背景から、地元ビジネスの活性化を企図して誕生した空間。ウェイティングバーやVIPルームを用意し、会合や接待利用も可能。現代の料亭と言える。
インテリアデザインを担当したcottoの八柳有子さんは、「依頼時に拓匠開発さんから、“地元を想う経営者同士で、千葉の風景を見ながらビジネスの話ができる場所を作りたい”と、地域の経済活性化に向けた展望を伺いました。限られた人が訪れ、熱を帯びたコミュニケーションがなされる店として、高級感と非日常を醸し出すデザインを模索していきました」と語る。
八柳さんは、店内のインテリアに加えて1階の専用エントランスもデザイン。動線の始まりとなるエレベーターホールでは、電球型の照明を複数灯直付けして劇場のような趣を与え、期待感を高める効果を狙った。エレベーターが開くと、緋毛氈をイメージした赤色の廊下が延びる。片側の壁面は、赤色からオレンジにグラデーションプリントを施したガラス。反対側の折り上げ天井には、赤色光の間接照明が配され、印象的な光が柔らかく全体に広がっている。

「ひいろ」廊下。右上部の折り上げ天井から赤い光が伸び、赤い床面や、反対側の赤からオレンジへとグラデーション加工されたガラスの色彩を深めている。左手前がウェイティングバー「アタラヨ」、中央が鉄板焼きがある「艸」、奥がVIPルーム「薗」という平面構成。
「建物の各階にテーマカラーが定められていて、『ひいろ』がある5階は赤だったのです。“熱あるところに人は集まる”という考えから、火の色が設定され、フロア名の由来にもなりました。例えば古くは赤金(あかがね)と呼ばれていた銅など、赤を連想させる様々なマテリアルを用いて、過剰になりすぎないようバランスを取りながら空間を組み立てていきました」
フロアには「間」と見立てた三つの空間が用意された。鉄板焼きカウンターが据えられたメインの部屋には赤色の左官や銅色のフード、最奥のVIPルームでは経年変化で赤褐色へと変化する木材、革のソファや緋色のベルベット製カーペット。一方で、手前に配されたウェイティングバーではコンクリートや古材など素の素材が使われており、奥に進むごとに色彩が深く濃く、艶やかに質感が変化していく構成だ。更に、照明が加わることで、色の力を最大限に高めた鮮烈な空間が立ち上がっている。

ウェイティングバー。ボトル棚の背景は銅板で、赤い光を仕込んでいる

VIPルーム。艶感のある素材で緋色を挿入した
飲食空間にカラーライティングを採用するための工夫
「ひいろ」という名前に、店内に散りばめられた赤色のマテリアル。そして空間を染め上げる赤色光の照明。内装に赤をキーカラーとする上で、照明にもカラーライティングを採用したのはなぜなのか。
「実を言うと、設計時は電球色程度のある程度あたたかみが感じられる色温度をイメージしていたのです」と八柳さんは背景を語る。照明には調光調色シリーズの「Synca」対応の照明器具が採用されており、幅広い色温度と121色の色光の再現が可能であった。
「現場で照明シーンを設定している中で、各素材の色彩が強く浮かび上がり、より空間の印象を高めてくれたのが赤色光でした。元々通過点である廊下にはエンターテインメント性を持たせたいと考えていたのですが、関係者全員で光を体感し、満場一致で現在の形となりました」

メインの鉄板焼きルーム。上部が抜けたグラデーションガラスの間仕切りを通して、廊下の間接光が窓に反射し、外の暗闇の中で広がる。カウンター周りはニュートラルな色の素材、色温度に設定することで、料理を邪魔しない工夫を施した
しかし食事を楽しむ空間において、食べ物を照らす照明器具は、そこでの体験を左右する重要な存在である。懸念点はなかったのだろうか。八柳さんは、その解決策を次のように説明する。
「実際に食事する空間のダウンライトは色温度を3000Kに設定し、料理の色味がシェフの方にもお客様にも綺麗に見えるようにしています。カウンターの色はベージュにするなど、食材が絡む部分はニュートラルであることを意識しました。鉄板焼きカウンターがあるメインの部屋に差し込む赤い光は、廊下に配した照明が、グラデーションガラスの間仕切り越しに見えているだけなのです」
仕切りの上部はグラデーション塗装を抜いていたため、上部から赤の間接光が全体に回りつつ、料理の色やシェフのパフォーマンスは邪魔しないように設計されていた訳だ。

1階の専用エントランスとなるエレベーターホール。劇場をイメージしたデザインで、入り口から高揚感を演出している
「私自身、カラーライティングを商空間に採用したのは初めての挑戦でした。これまでは、舞台やイベントなど用途が限定した場所で使われるものだと思い込んでいました。しかし今回は、非日常を生み出し劇場に訪れたようなワクワクを創出したいと考えていたこともあり、照明を赤にしたことでそのコンセプトをより明確に表現できたと感じています」
調光調色対応という器具のスペックも、カラーライティングのハードルを下げてくれたという。施工後も端末を用いた設定変更が可能なので、いざとなれば白に戻すことができる安心感は大きい。スタッフの作業が生じるクローズ時は一般的な色温度の設定になっている。
八柳さんはプロジェクトを通して、「“光で遊ぶことができる”と気付くきっかけになりました。今後は季節によって見せ方を変えるなど、違う色光での演出も試してみたいです」とこれからへの期待を語る。ちなみに「the RECORDS」では、建物全体でSynca対応の照明器具が採用されており、1、2階のカフェではウェディングやパーティー時に活用されたり、オフィスでも社内イベントなどの際に演出としてカラーライティングを取り入れているようだ。
色が持つ装飾的な力に、光を掛け合わせることで、最大限に引き出していくことができる。ここで過ごした時間は、赤い灯と共に、記憶に焼き付くことだろう。「ひいろ」は、光と色の可能性を教えてくれるプロジェクトであった。
写真提供:株式会社 拓匠開発
八柳有子(やつやなぎ・ゆうこ)
東京理科大学理工学部建築学科、同大学理工学研究科建築学専攻終了。
卒業後、IDEE、設計事務所勤務を経てcottoを安齋悠子と設立。住宅、商業の用途を超えて、人、物、場所、時間をつないでいくものを提案する。
素材やディテールを追求し、あらゆる要素が調和する空間を目指す。
Writer
ヒカリイク編集部
『ヒカリイク』は、人と光に向き合うデザイン情報サイトです。
これからの空間デザインに求められる照明の未来から、今すぐ使えるお役立ち情報まで、
照明についてのあらゆるニュースをお届けします。