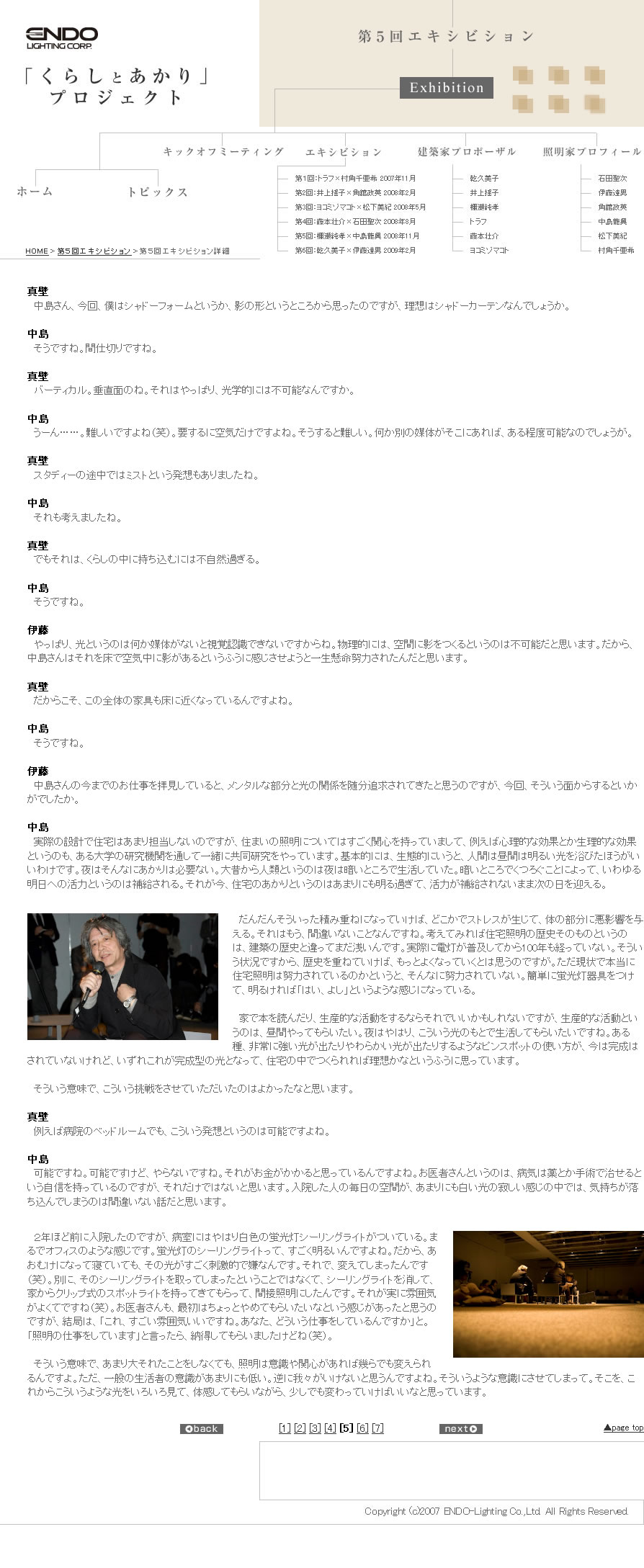真壁
中島さん、今回、僕はシャドーフォームというか、影の形というところから思ったのですが、理想はシャドーカーテンなんでしょうか。
中島
そうですね。間仕切りですね。
真壁
バーティカル。垂直面のね。それはやっぱり、光学的には不可能なんですか。
中島
うーん……。難しいですよね(笑)。要するに空気だけですよね。そうすると難しい。何か別の媒体がそこにあれば、ある程度可能なのでしょうが。
真壁
スタディーの途中ではミストという発想もありましたね。
中島
それも考えましたね。
真壁
でもそれは、くらしの中に持ち込むには不自然過ぎる。
中島
そうですね。
伊藤
やっぱり、光というのは何か媒体がないと視覚認識できないですからね。物理的には、空間に影をつくるというのは不可能だと思います。だから、中島さんはそれを床で空気中に影があるというふうに感じさせようと一生懸命努力されたんだと思います。
真壁
だからこそ、この全体の家具も床に近くなっているんですよね。
中島
そうですね。
伊藤
中島さんの今までのお仕事を拝見していると、メンタルな部分と光の関係を随分追求されてきたと思うのですが、今回、そういう面からするといかがでしたか。
中島
実際の設計で住宅はあまり担当しないのですが、住まいの照明についてはすごく関心を持っていまして、例えば心理的な効果とか生理的な効果というのも、ある大学の研究機関を通して一緒に共同研究をやっています。基本的には、生態的にいうと、人間は昼間は明るい光を浴びたほうがいいわけです。夜はそんなにあかりは必要ない。大昔から人類というのは夜は暗いところで生活していた。暗いところでくつろぐことによって、いわゆる明日への活力というのは補給される。それが今、住宅のあかりというのはあまりにも明る過ぎて、活力が補給されないまま次の日を迎える。

だんだんそういった積み重ねになっていけば、どこかでストレスが生じて、体の部分に悪影響を与える。それはもう、間違いないことなんですね。考えてみれば住宅照明の歴史そのものというのは、建築の歴史と違ってまだ浅いんです。実際に電灯が普及してから100年も経っていない。そういう状況ですから、歴史を重ねていけば、もっとよくなっていくとは思うのですが。ただ現状で本当に住宅照明は努力されているのかというと、そんなに努力されていない。簡単に蛍光灯器具をつけて、明るければ「はい、よし」というような感じになっている。
家で本を読んだり、生産的な活動をするならそれでいいかもしれないですが、生産的な活動というのは、昼間やってもらいたい。夜はやはり、こういう光のもとで生活してもらいたいですね。ある種、非常に強い光が出たりやわらかい光が出たりするようなピンスポットの使い方が、今は完成はされていないけれど、いずれこれが完成型の光となって、住宅の中でつくられれば理想かなというふうに思っています。
そういう意味で、こういう挑戦をさせていただいたのはよかったなと思います。
真壁
例えば病院のベッドルームでも、こういう発想というのは可能ですよね。
中島
可能ですね。可能ですけど、やらないですね。それがお金がかかると思っているんですよね。お医者さんというのは、病気は薬とか手術で治せるという自信を持っているのですが、それだけではないと思います。入院した人の毎日の空間が、あまりにも白い光の寂しい感じの中では、気持ちが落ち込んでしまうのは間違いない話だと思います。

2年ほど前に入院したのですが、病室にはやはり白色の蛍光灯シーリングライトがついている。まるでオフィスのような感じです。蛍光灯のシーリングライトって、すごく明るいんですよね。だから、あおむけになって寝ていても、その光がすごく刺激的で嫌なんです。それで、変えてしまったんです(笑)。別に、そのシーリングライトを取ってしまったということではなくて、シーリングライトを消して、家からクリップ式のスポットライトを持ってきてもらって、間接照明にしたんです。それが実に雰囲気がよくてですね(笑)。お医者さんも、最初はちょっとやめてもらいたいなという感じがあったと思うのですが、結局は、「これ、すごい雰囲気いいですね。あなた、どういう仕事をしているんですか」と。「照明の仕事をしています」と言ったら、納得してもらいましたけどね(笑)。
そういう意味で、あまり大それたことをしなくても、照明は意識や関心があれば幾らでも変えられるんですよ。ただ、一般の生活者の意識があまりにも低い。逆に我々がいけないと思うんですよね。そういうような意識にさせてしまって。そこを、これからこういうような光をいろいろ見て、体感してもらいながら、少しでも変わっていけばいいなと思っています。