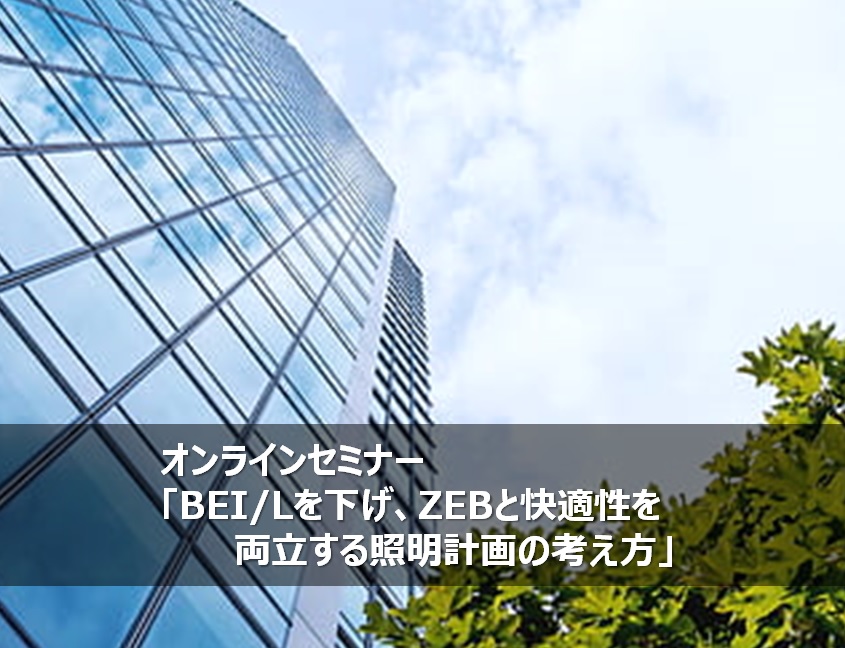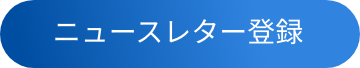省エネ規制と照明デザイン
――vol.5 照明デザイナーLOOP LIGHTING中村亮子氏に聞く
2025.9.1

4 Times Square Convene One Five One(Photo Credit: Jeremy Frechette)
4 Times Squareでは、Ketra システムを導入。 無線で個別にアドレス指定可能な光源ネットワークにより、複雑な配線を不要とし、柔軟なゾーニングや再プログラミングを可能にした。これにより、省エネ規制への対応と同時に、調光調色など設計の自由度も高めることが出来た。
省エネ規制と照明デザインの関わり方について、諸外国での取り組みを紹介する本連載。
前回記事でアメリカの省エネ規制と照明デザインについて紹介したが、実際に現場に立つ照明デザイナー達は、「省エネ規制」という枠の中でどのように環境配慮しつつ創造性の高いデザインに取り組んでいるのだろうか。また、彼らはそうした実状に対しどのようなことを感じているのか。
今回はアメリカで照明デザインの実務経験を積んだ照明デザイナーにインタビューを行った。
お話をうかがったのは、アメリカ・ニューヨークに拠点を持ち、日本やイタリアなどにグローバルなチームを有する建築照明デザイン事務所LOOP LIGHTINGの照明デザイナー、中村亮子さん。
2006年からニューヨークでのキャリアをスタートし、2015年に2人のパートナーと共にLOOP LIGHTINGを立ち上げた。2019年からは日本支社の代表として、現在も主に日本とアメリカのプロジェクトで活躍している。
アメリカの省エネ規制
中村さんがアメリカで照明デザイナーとして働き始めた時にはもうすでに省エネ規制への取り組みはデザイン業務の一環としてあったという。
「私が渡米したころはまだ蛍光灯やメタルハライドランプが光源の中心で、例えば電源の出力を調整して電力量を下げるなど、省エネ規制をいかにクリアするか・効率化するかは結構大変なことでした。LED化で器具自体がかなり効率化され、今はそうした調整はもう必要ありませんが、次第にLEDへと移行していく過程を見られたことは貴重な経験になったと思います。エナジーコードは改正ごとに規制内容が厳しくなっていますが、高効率・高性能な照明器具が常に開発され続けているので、実際のところ規制によってデザインを制限されるという感覚はあまりなく、むしろ初期の頃よりもやりやすくなっていると感じます。」

Classic Car Club Manhattan(Photo Credit: Marc-Thorpe)
Casambiによる無線制御を用いることで、照明の調光やグループ操作をモバイル端末などからワイヤレスに実現。これにより、特定の時間やイベント、雰囲気に応じた光のシーン設定が可能となり、会員制ラウンジのムードを柔軟にコントロール。
アメリカでは省エネ規制(エナジーコード、vol.4記事を参照)を照明デザイナーが基本設計の段階から確認することが一般的だというが、それはどうしてなのだろうか。
「私たちはデザインの専門家なので、最終的な確認や申請などは設備設計者の承認が必要ですが、省エネ規制を満たすための資料を設備設計者にあとから確認してもらって調整するよりも、デザインの意図を理解している照明デザイナーが設計初期段階から並行してチェックしたほうがずっと早く的確にバランスをとることができます。エナジーコードは州ごと、さらには同じ州内でも都市ごとに大きく異なるので、案件ごとに規制内容が異なる点も考慮する必要があります。商業施設やオフィスが多いフィラデルフィア・二ューヨーク・ワシントンDCなどは特に規制が厳しいです。また最近では制御システムも省エネ規制に必須のものとなり、デザイン業務は以前よりも複雑化してきていると感じます。照明デザイナーに求められるのはデザイン力だけではなく、こうした規制を満たす総合力のようなものも必要で、全体的に難易度が高いと感じます。」
日本とアメリカの違い

Avalon Bay Headquarters(Photo Credit: Halkin Mason Photography)
EVホール折り上げ天井に組み込まれた象徴的なペンダント照明と、ルーバー天井に仕込まれたスリムダウンライトのリズムが呼応し、EVホールに奥行きと洗練された印象を与える。
アメリカでは日本の総合照明メーカーのような会社は少なく、中小の照明メーカーが数多く存在する。ダウンライト、リニアライト、意匠系など、各社それぞれ特化した製品を製造しており、照明デザイナーは多種多様なメーカーの製品を取り合わせて設計を行う必要がある。デザインに対し最適な器具を選定することも照明デザイナー重要な役割のひとつだ。
「日本で照明設計を始めたときに感じたのが、デザインに値する高効率な器具の種類の少なさです。最近では日本の器具も少しずつ良い製品が増えてきていますが、感覚的にはアメリカよりも5~8年くらい遅れているという印象です。もちろん産業規模の違いはあると思うのですが、アメリカには小口径ながら器具効率の高いグレアレスタイプの器具や、トリムレス・配光・取付パーツなどのバリエーションも日本よりかなり多く、効果的にデザインを実現させるための器具の選択肢がたくさんあります。こうした状況をずっと不思議に思っていましたが、じつは省エネ規制が関係しているのではないかと考えるようになりました。というのも省エネ規制があるために、照明メーカーは高効率で良質の器具を作らざるを得ないのではないでしょうか。照明制御についても同様で、多くのメーカーがオープンプロトコルのシステムを導入し、メーカー同士が足並みを揃え協力しながら省エネ規制に対応しています。」
また設計時の推奨照度の設定値にも大きな違いがあるという。
「アメリカでは北米照明学会が推奨照度を定めているのですが、日本やアジア圏の国のよりも推奨照度の設定値が低いことが多いです。例えばアメリカではオフィスの机上面照度は300-350ルクス程度となっていますが、日本は500-750ルクスでほぼ倍の数値です。曇天時などはアメリカでも350ルクスだと少し暗く感じることがあるのですが、デスクライトが補助光としてあれば問題はありませんし、コンセントタイプの器具は省エネ規制の対象外になっているので、省エネ規制が快適性を阻むことがないように設計できます。こうした推奨照度の違いは日本人と西洋人で瞳の色の違いによる光の感じ方の差もあるかもしれませんし、文化的な側面もあるかもしれません。」

Consilio Miami(Photo Credit: Moris Moreno photography)
温かみと躍動感に包まれた空間の中、巨大なカーブしたLEDメディアウォールと、それを取り囲む間接照明の柔らかな光が、動的かつ洗練された体験を生み出した。
世界に先駆けて照明デザインを発展させてきたアメリカはエンターテインメント大国でもある。演出的な光は省エネ規制の中でどのように扱われているのだろうか?
「演出的な照明や美術館などの文化施設に使用される照明は省エネ規制の対象外になるものもあり、その場合は個別の照明ガイドラインに沿って計画を進めます。街のランドマークや景観に対しても同様のことが言えます。省エネ規制があるとはいえ、空間の目的に合わせてケースバイケースでデザインを行っています。前述のようにアメリカは省エネ規制自体のバリエーションも多いですし、器具や制御のバリエーションも多様化しています。照明デザイナーがいないと高いデザイン性と省エネを両立させることができない、特に商業施設などにおいては照明デザイナーがいないとプロジェクトが成り立たないという状況は広く認識され、照明デザイナーが重宝されていると感じます。」
省エネ規制のメリット

Convene at 333 North Green in Chicago(Photo Credit:Tom Harris Architectural Photography)
Lutron AtenaとViveによるスマート制御により、暖かな間接光と色のアクセントが調和し、動きと集中を促す柔軟な光環境を実現。コンベンシングスタイルの会議空間に、快適性と適応性を両立。
最後に省エネ規制があることのメリットと日本の展望についてうかがった。
「アメリカでは省エネ規制があることが当たり前すぎて、メリットやデメリットについて考えたことがありませんでした。規制がないことでデザインの自由度は高くなるだろうとは思うのですが…日本で仕事を始めた時はむしろこうした規制や確認項目が業務の中にないことにとても驚きました。
省エネ規制があることで空間や照明デザインの質は絶対に向上していくと思います。アメリカでは明確な規制があるため、照明デザイナーがクリエイティブにならなければ条件をクリアし、価値の高い魅力的な空間を提案・実現させることができません。また照明メーカーも規制をクリアしうる質の高い器具を作らなければ器具が売れません。品質の高い器具はコストもかかりますし、もちろん照明デザイナーを雇うことも安くはありません。しかし良いものをつくるためには対価がかかるということを、施主も設計者も十分に理解しているのだと思います。省エネ規制が関係者全員の意識を上げていくことはメリットと言えるのではないでしょうか。
日本はモノづくりの技術水準や作り手一人一人の意識の高さなどポテンシャルはものすごく高い。ただ革命的なイノベーションを感じるようなデザインは少ないと感じます。日本は陰影礼賛などもともと暗さやメリハリを良しとしてきた文化があり、こうした日本人の光の感性に学ぶことからも省エネ規制がプラスに働くことを期待しています。」
中村 亮子(なかむら・りょうこ)
LOOP Lighting NYオフィス共同経営者・京都オフィス代表
2003:武蔵野美術大学造形学部卒業
2006:Kugler Ning Lighting 入社
2013:Linnaea Tillett Lighting Design Associates 入社
2015:LOOP Lightingを共同経営者2名と設立
2020:LOOP Lighting 日本支社京都オフィス設立
主なプロジェクト:70 Hudson Street Lobby、Convene Projects、The Shinmonzen レストラン、バスターミナル東京八重洲 第1期エリア、兵庫県立淡路夢舞台公苑温室「あわじグリーン館」 改修など
https://www.looplighting.nyc/