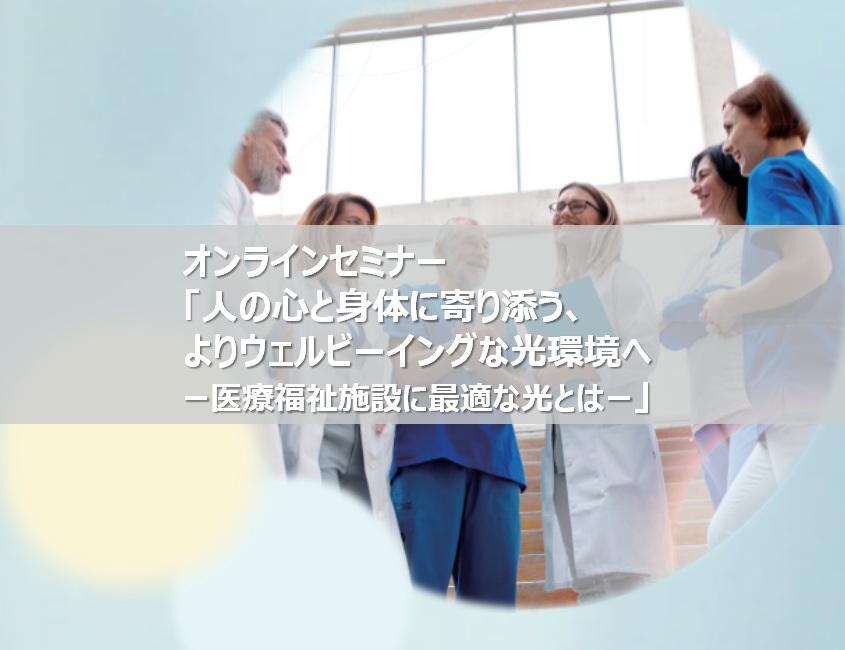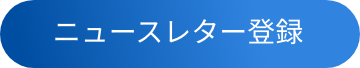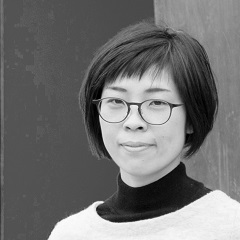はじめに
建築設計に携わる照明デザイナーの多くが、用途に則した最小限の光を用いて、機能的で魅力的な空間を作る「引き算の美学」に基づいてデザインを行っている。しかし近年、その引き算にエビデンスが求められるようになってきたことを多くの方が実感しているのではないだろうか。
私の場合はアメリカに拠点を持つ照明デザイン事務所のプロジェクトメンバーに加わった数年前、LEED認証取得を目指す某プロジェクトに携わったときのことだ。使用する電力量をかなり抑えて加点を得る必要があり、私達は設計の初期段階から電力量を確認し、器具効率が高い器具を中心に選定することで、厳しい条件をクリアすることができたのだった…こう書くと当たり前のことのように聞こえるかもしれないが、当時の私は意匠最重視で器具選定をすることが大前提で、多くのプロジェクトにおいて器具効率をほとんど意識していなかったため、意匠を重視しながらも電力量を最優先に考え器具選定を行ったことは少なからずカルチャーショックな出来事だった。このプロジェクトを通じて、アメリカでは認証取得の有無に関わらず、空間規模や用途ごとに使用できる電力量制限があること、照明デザイナーは設計の初期段階から電力量を確認しつつデザインを行うことが一般的であることを知った。
それ以来、自分の省エネに関する意識や知識がずいぶんアップデートできていないのではと危機感を感じるようになった。空間に適した光環境を提案し、消費電力の少ないLED器具を中心に選定しているのだから、当然省エネにも貢献しているだろうと漠然と信じていたところがあった。現在建築物には数多くの省エネ規制が設定されているが、照明デザインも例外ではない。漠然ではなく、具体的な数字を示していく必要があるのだ。
省エネに関する目標設定・法規制の内容は国ごとに異なるが、諸外国の中には照明デザイナーが設計初期段階から省エネ規制に準じた提案を行い、環境負荷を低減しながら魅力的で快適な照明設計に取り組んでいるという事実があり、日本ではまだあまり広く知られていないように思う。そこで本連載では日本・EU・アメリカの照明に関連する省エネ規制(非住宅建築物)を取り上げ、その概要や照明デザイナーの関わり方について紹介したい。また欧米での照明デザイン経験を持つ照明デザイナーへのインタビューを行い、省エネ規制をどのようにポジティブにデザインに生かせるか等、率直な意見を伺った。
日本においても省エネへの取り組みがよりいっそう求められていく中で、こうした先進的な取り組みを知っておくことは非常に有意義であると思う。多くの方にとって今後のデザインや設計のヒントとなれば幸いである。
vol.1「日本の省エネ規制と照明デザイン」
背景
エネルギー自給率が低い日本では石油や天然ガスなどの燃料を輸入に頼らざるを得ず、1970年代の2度のオイルショックを契機に、本格的な省エネ対策に取り組み始めた。1997年の京都議定書、2015年のパリ協定採択を経て、日本では2030年度までに温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減し、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルの実現を目標としている。
※参考:国土交通省「建築物省エネ法のページ」
日本の省エネへの取り組みは世界全体で見れば比較的進んでいると考えられ、温室効果ガスの排出量も減少傾向にあるが、上記の目標を達成するため、またエネルギー自給率の低さなどその他の課題も考慮すれば、今後さらに厳しい規制へと発展していくことは想像に難くない。
建築物省エネ法
「建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)」は建築物の省エネに関わる最も主要な法規制だ。その名の通り、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的として制定され、2025年4月からは原則すべての新築住宅・非住宅で省エネ基準適合を受けることが義務化される。照明や空調などの建築設備に関する「一次エネルギー消費量基準」、断熱性能に関する「外皮基準」に対し、省エネ基準適合が求められる。
※参考:国土交通省「省エネ基準適合義務化」
照明に関わる「一次エネルギー消費量基準」をクリアするためには、まず照明や空調など対象の建築設備において設計上想定される総エネルギー消費量(=設計一次エネルギー消費量)確認する必要がある。次にこれを建築規模など与条件によって決定される基準的な総エネルギー消費量(=基準一次エネルギー消費量)で割り、BEI(Building Energy Index)値を算出する。複雑な計算を伴うが、大まかに表現すればBEI値が1以下、つまり設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量以下であれば、適合基準クリアとなる(2,000㎡以上の大型建築物は、建物用途によって0.75-0.85が基準となる)。
照明項目においては、スケジュール制御や明るさ検知制御を導入することで、設計一次エネルギー消費量に有利な係数を適用できるなどの緩和措置がある。
適合義務以外にもBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)やCASBEE(建築環境総合性能評価システム)など建築の性能を客観的に評価する国内の認証制度があり、省エネ貢献への理解を広げていくことを促している。
なお、省エネ目標達成に向けて大きな貢献が期待されているZEB(Net Zero Energy Building)についても、原則として一次エネルギー消費量が評価指標となっており、BEI値においてZEBランクが判定される。

(左)省エネ性能ラベル/(右)エネルギー消費性能の評価書
ZEBとは? 取得のメリットと照明でZEBを実現するポイントも紹介
照明デザイナーの関わり方
日本での省エネ規制に関する申請書の作成や内容の確認は、意匠設計者や設備設計者によってなされることが多く、これまでは照明デザイナーが初期計画段階で省エネ規制に対する具体的な消費電力数値に準じて設計を行う機会はそれほど多くなかったと思われる。しかし、建築物省エネ法の改正や昨今のエネルギー事情により、今後は設計初期段階から消費電力の上限をあらかじめ想定・確認しながら、照明デザインを進めていく場面が増えることが予想される。
注意したい点
日本国内の建築物に関する省エネ規制は段階的に導入・改正が進められてきたが、光環境の在り方や照度設定に関しては言及されていない。そのため数値的に省エネ基準をクリアしていても、安全で快適な空間が実現できないなど、光の質に関するトラブルが増加する懸念がある。
また、スケジュール制御や明るさ検知制御など規制緩和のために導入した設備が、実際には活用されておらず、運用時の省エネに寄与していないケースがあるという。設計や施工段階だけでなく、実際の運営者への導入意義や運用方法の確実な伝達を徹底することも欠かせない。
空間の印象は光だけでなく、素材や色、空間の形状などによっても大きく変化するため、数値のみで照明デザインの良し悪しを判断することは非常に難しいが、JIS照度基準や、輝度に対する理解を深めることは照明デザインを総合的な視点で進めていく大きな助けになるだろう。
JISの照度基準を正しく理解する
輝度とは? 照度との違いや輝度対比まで分かりやすく解説!
まとめ
実のところ私自身も省エネ適判と並走しながらのデザイン経験がまだそれほど多くなく、引き続き実践と理解を深める必要があると感じている。しかしながら重要なことは数値目標の達成だけではなく、こうした取り組みや学びを通じて、私たち一人ひとりが環境意識を高めていくことにあるのではないだろうか?光の質へのこだわりを失わずに、人にも環境にも優しい光のデザインを目指したい。
次回はヨーロッパの省エネ規制について紹介する。
Writer
廣木 花織(ひろき・かおり)
照明デザイナー
多摩美術大学環境デザイン学科を卒業後、有限会社内原智史デザイン事務所に照明デザイナーとして入社。同事務所を退職後、北欧の光文化への興味からデンマークへ留学。2018年よりLyshus(リュスフース)代表。2021年よりLOOP Lightingシニアアソシエイトとしてプロジェクト参画。都市計画から建築・インテリア・ランドスケープ・イルミネーション・ディスプレイまで、他種多様な空間用途での照明設計に幅広く携わる。
また多摩美術大学建築・環境デザイン学科非常勤講師として後進の指導にも力を注いでいる。