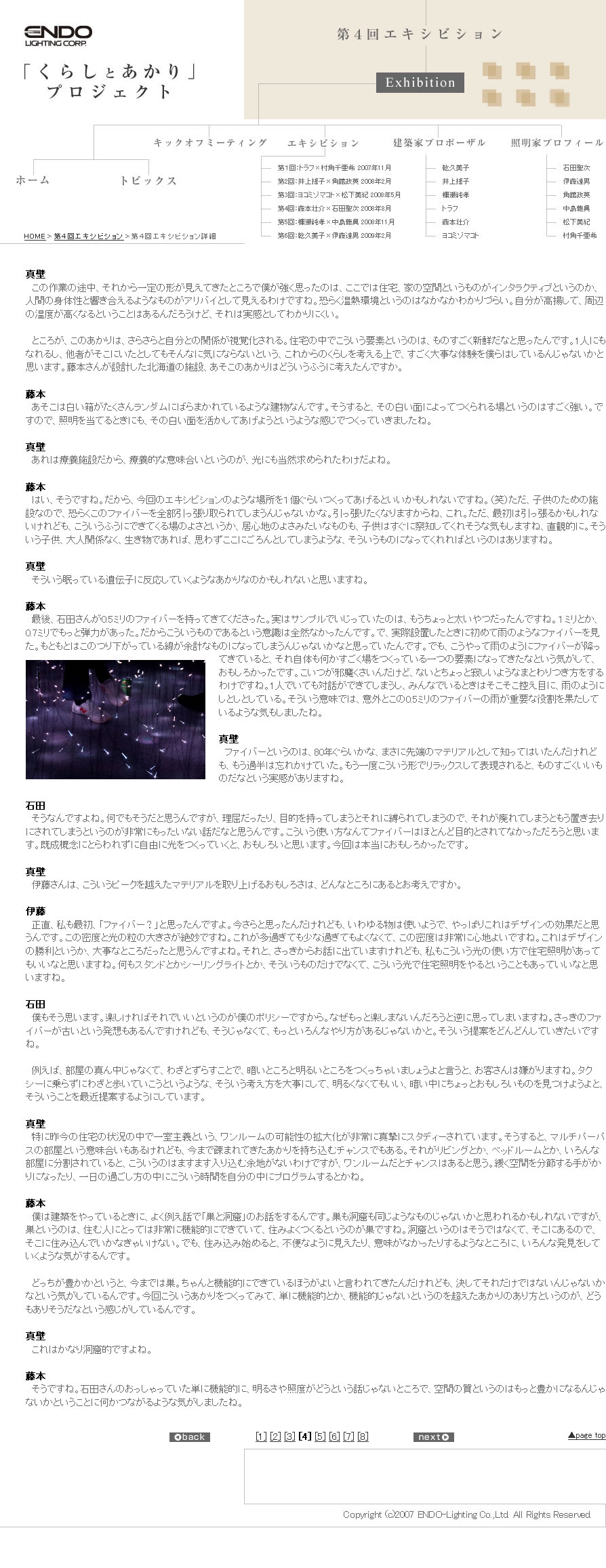真壁
この作業の途中、それから一定の形が見えてきたところで僕が強く思ったのは、ここでは住宅、家の空間というものがインタラクティブというのか、人間の身体性と響き合えるようなものがアリバイとして見えるわけですね。恐らく温熱環境というのはなかなかわかりづらい。自分が高揚して、周辺の温度が高くなるということはあるんだろうけど、それは実感としてわかりにくい。
ところが、このあかりは、さらさらと自分との関係が視覚化される。住宅の中でこういう要素というのは、ものすごく新鮮だなと思ったんです。1人にもなれるし、他者がそこにいたとしてもそんなに気にならないという、これからのくらしを考える上で、すごく大事な体験を僕らはしているんじゃないかと思います。藤本さんが設計した北海道の施設、あそこのあかりはどういうふうに考えたんですか。
藤本
あそこは白い箱がたくさんランダムにばらまかれているような建物なんです。そうすると、その白い面によってつくられる場というのはすごく強い。ですので、照明を当てるときにも、その白い面を活かしてあげようというような感じでつくっていきましたね。
真壁
あれは療養施設だから、療養的な意味合いというのが、光にも当然求められたわけだよね。
藤本
はい、そうですね。だから、今回のエキシビションのような場所を1個ぐらいつくってあげるといいかもしれないですね。(笑)ただ、子供のための施設なので、恐らくこのファイバーを全部引っ張り取られてしまうんじゃないかな。引っ張りたくなりますからね、これ。ただ、最初は引っ張るかもしれないけれども、こういうふうにできてくる場のよさというか、居心地のよさみたいなものも、子供はすぐに察知してくれそうな気もしますね、直観的に。そういう子供、大人関係なく、生き物であれば、思わずここにごろんとしてしまうような、そういうものになってくれればというのはありますね。
真壁
そういう眠っている遺伝子に反応していくようなあかりなのかもしれないと思いますね。
藤本
最後、石田さんが0.5ミリのファイバーを持ってきてくださった。実はサンプルでいじっていたのは、もうちょっと太いやつだったんですね。1ミリとか、0.7ミリでもっと弾力があった。だからこういうものであるという意識は全然なかったんです。で、実際設置したときに初めて雨のようなファイバーを見た。もともとはこのつり下がっている線が余計なものになってしまうんじゃないかなと思っていたんです。 でも、こうやって雨のようにファイバーが降ってきていると、それ自体も何かすごく場をつくっている一つの要素になってきたなという気がして、おもしろかったです。こいつが邪魔くさいんだけど、ないとちょっと寂しいようなまとわりつき方をするわけですね。1人でいても対話ができてしまうし、みんなでいるときはそこそこ控え目に、雨のようにしとしとしている。そういう意味では、意外とこの0.5ミリのファイバーの雨が重要な役割を果たしているような気もしましたね。
でも、こうやって雨のようにファイバーが降ってきていると、それ自体も何かすごく場をつくっている一つの要素になってきたなという気がして、おもしろかったです。こいつが邪魔くさいんだけど、ないとちょっと寂しいようなまとわりつき方をするわけですね。1人でいても対話ができてしまうし、みんなでいるときはそこそこ控え目に、雨のようにしとしとしている。そういう意味では、意外とこの0.5ミリのファイバーの雨が重要な役割を果たしているような気もしましたね。
真壁
ファイバーというのは、80年ぐらいかな、まさに先端のマテリアルとして知ってはいたんだけれども、もう過半は忘れかけていた。もう一度こういう形でリラックスして表現されると、ものすごくいいものだなという実感がありますね。
石田
そうなんですよね。何でもそうだと思うんですが、理屈だったり、目的を持ってしまうとそれに縛られてしまうので、それが廃れてしまうともう置き去りにされてしまうというのが非常にもったいない話だなと思うんです。こういう使い方なんてファイバーはほとんど目的とされてなかっただろうと思います。既成概念にとらわれずに自由に光をつくっていくと、おもしろいと思います。今回は本当におもしろかったです。
真壁
伊藤さんは、こういうピークを越えたマテリアルを取り上げるおもしろさは、どんなところにあるとお考えですか。
伊藤
正直、私も最初、「ファイバー?」と思ったんですよ。今さらと思ったんだけれども、いわゆる物は使いようで、やっぱりこれはデザインの効果だと思うんです。この密度と光の粒の大きさが絶妙ですね。これが多過ぎても少な過ぎてもよくなくて、この密度は非常に心地よいですね。これはデザインの勝利というか、大事なところだったと思うんですよね。それと、さっきからお話に出ていますけれども、私もこういう光の使い方で住宅照明があってもいいなと思いますね。何もスタンドとかシーリングライトとか、そういうものだけでなくて、こういう光で住宅照明をやるということもあっていいなと思いますね。
石田
僕もそう思います。楽しければそれでいいというのが僕のポリシーですから。なぜもっと楽しまないんだろうと逆に思ってしまいますね。さっきのファイバーが古いという発想もあるんですけれども、そうじゃなくて、もっといろんなやり方があるじゃないかと。そういう提案をどんどんしていきたいですね。
例えば、部屋の真ん中じゃなくて、わざとずらすことで、暗いところと明るいところをつくっちゃいましょうよと言うと、お客さんは嫌がりますね。タクシーに乗らずにわざと歩いていこうというような、そういう考え方を大事にして、明るくなくてもいい、暗い中にちょっとおもしろいものを見つけようよと、そういうことを最近提案するようにしています。
真壁
特に昨今の住宅の状況の中で一室主義という、ワンルームの可能性の拡大化が非常に真摯にスタディーされています。そうすると、マルチパーパスの部屋という意味合いもあるけれども、今まで疎まれてきたあかりを持ち込むチャンスでもある。それがリビングとか、ベッドルームとか、いろんな部屋に分割されていると、こういうのはますます入り込む余地がないわけですが、ワンルームだとチャンスはあると思う。緩く空間を分節する手がかりになったり、一日の過ごし方の中にこういう時間を自分の中にプログラムするとかね。
藤本
僕は建築をやっているときに、よく例え話で「巣と洞窟」のお話をするんです。巣も洞窟も同じようなものじゃないかと思われるかもしれないですが、巣というのは、住む人にとっては非常に機能的にできていて、住みよくつくるというのが巣ですね。洞窟というのはそうではなくて、そこにあるので、そこに住み込んでいかなきゃいけない。でも、住み込み始めると、不便なように見えたり、意味がなかったりするようなところに、いろんな発見をしていくような気がするんです。
どっちが豊かかというと、今までは巣。ちゃんと機能的にできているほうがよいと言われてきたんだけれども、決してそれだけではないんじゃないかなという気がしているんです。今回こういうあかりをつくってみて、単に機能的とか、機能的じゃないというのを超えたあかりのあり方というのが、どうもありそうだなという感じがしているんです。
真壁
これはかなり洞窟的ですよね。
藤本
そうですね。石田さんのおっしゃっていた単に機能的に、明るさや照度がどうという話じゃないところで、空間の質というのはもっと豊かになるんじゃないかということに何かつながるような気がしましたね。