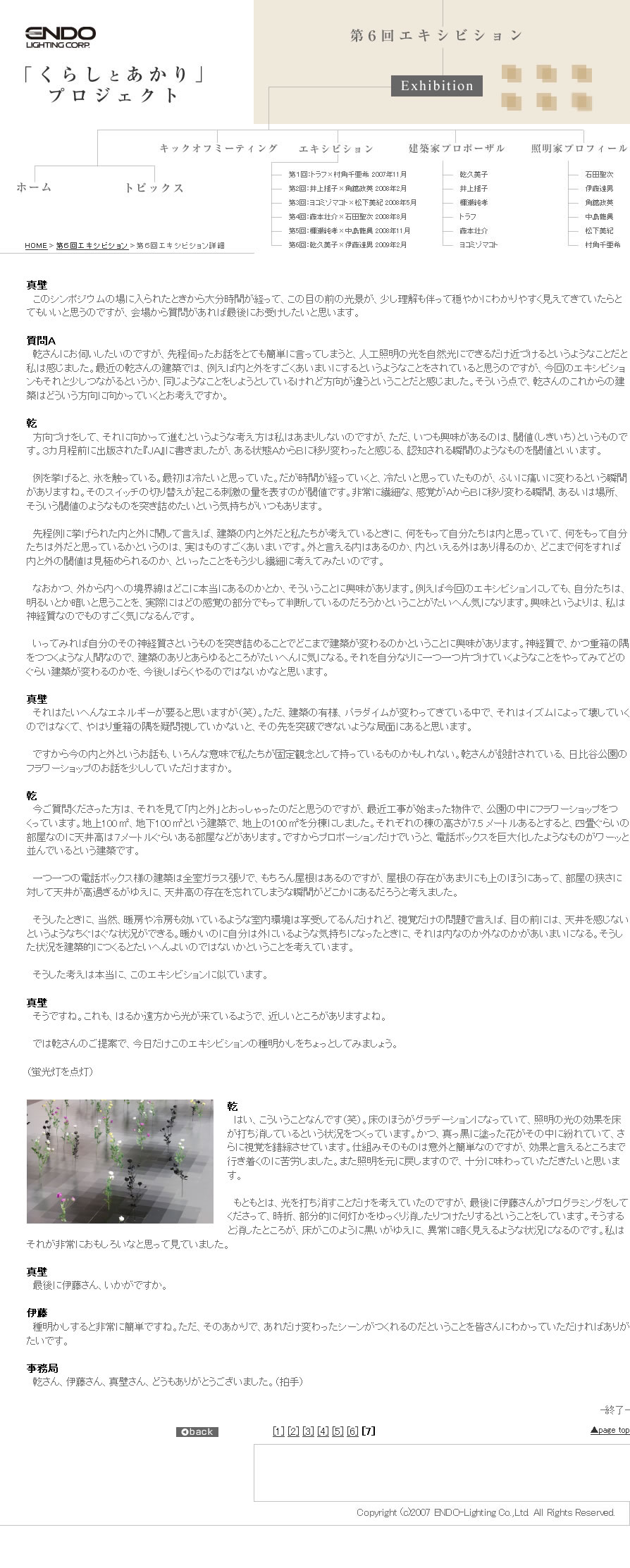真壁
このシンポジウムの場に入られたときから大分時間が経って、この目の前の光景が、少し理解も伴って穏やかにわかりやすく見えてきていたらとてもいいと思うのですが、会場から質問があれば最後にお受けしたいと思います。
質問A
乾さんにお伺いしたいのですが、先程伺ったお話をとても簡単に言ってしまうと、人工照明の光を自然光にできるだけ近づけるというようなことだと私は感じました。最近の乾さんの建築では、例えば内と外をすごくあいまいにするというようなことをされていると思うのですが、今回のエキシビションもそれと少しつながるというか、同じようなことをしようとしているけれど方向が違うということだと感じました。そういう点で、乾さんのこれからの建築はどういう方向に向かっていくとお考えですか。
乾
方向づけをして、それに向かって進むというような考え方は私はあまりしないのですが、ただ、いつも興味があるのは、閾値(しきいち)というものです。3カ月程前に出版された『JA』に書きましたが、ある状態AからBに移り変わったと感じる、認知される瞬間のようなものを閾値といいます。
例を挙げると、氷を触っている。最初は冷たいと思っていた。だが時間が経っていくと、冷たいと思っていたものが、ふいに痛いに変わるという瞬間がありますね。そのスイッチの切り替えが起こる刺激の量を表すのが閾値です。非常に繊細な、感覚がAからBに移り変わる瞬間、あるいは場所、そういう閾値のようなものを突き詰めたいという気持ちがいつもあります。
先程例に挙げられた内と外に関して言えば、建築の内と外だと私たちが考えているときに、何をもって自分たちは内と思っていて、何をもって自分たちは外だと思っているかというのは、実はものすごくあいまいです。外と言える内はあるのか、内といえる外はあり得るのか、どこまで何をすれば内と外の閾値は見極められるのか、といったことをもう少し繊細に考えてみたいのです。
なおかつ、外から内への境界線はどこに本当にあるのかとか、そういうことに興味があります。例えば今回のエキシビションにしても、自分たちは、明るいとか暗いと思うことを、実際にはどの感覚の部分でもって判断しているのだろうかということがたいへん気になります。興味というよりは、私は神経質なのでものすごく気になるんです。
いってみれば自分のその神経質さというものを突き詰めることでどこまで建築が変わるのかということに興味があります。神経質で、かつ重箱の隅をつつくような人間なので、建築のありとあらゆるところがたいへんに気になる。それを自分なりに一つ一つ片づけていくようなことをやってみてどのぐらい建築が変わるのかを、今後しばらくやるのではないかなと思います。
真壁
それはたいへんなエネルギーが要ると思いますが(笑)。ただ、建築の有様、パラダイムが変わってきている中で、それはイズムによって壊していくのではなくて、やはり重箱の隅を疑問視していかないと、その先を突破できないような局面にあると思います。
ですから今の内と外というお話も、いろんな意味で私たちが固定観念として持っているものかもしれない。乾さんが設計されている、日比谷公園のフラワーショップのお話を少ししていただけますか。
乾
今ご質問くださった方は、それを見て「内と外」とおっしゃったのだと思うのですが、最近工事が始まった物件で、公園の中にフラワーショップをつくっています。地上100 ㎡、地下100 ㎡という建築で、地上の100 ㎡を分棟にしました。それぞれの棟の高さが7.5 メートルあるとすると、四畳ぐらいの部屋なのに天井高は7メートルぐらいある部屋などがあります。ですからプロポーションだけでいうと、電話ボックスを巨大化したようなものがワーッと並んでいるという建築です。
一つ一つの電話ボックス様の建築は全室ガラス張りで、もちろん屋根はあるのですが、屋根の存在があまりにも上のほうにあって、部屋の狭さに対して天井が高過ぎるがゆえに、天井高の存在を忘れてしまうな瞬間がどこかにあるだろうと考えました。
そうしたときに、当然、暖房や冷房も効いているような室内環境は享受してるんだけれど、視覚だけの問題で言えば、目の前には、天井を感じないというようなちぐはぐな状況ができる。暖かいのに自分は外にいるような気持ちになったときに、それは内なのか外なのかがあいまいになる。そうした状況を建築的につくるとたいへんよいのではないかということを考えています。
そうした考えは本当に、このエキシビションに似ています。
真壁
そうですね。これも、はるか遠方から光が来ているようで、近しいところがありますよね。
では乾さんのご提案で、今日だけこのエキシビションの種明かしをちょっとしてみましょう。
(蛍光灯を点灯)

乾
はい、こういうことなんです(笑)。床のほうがグラデーションになっていて、照明の光の効果を床が打ち消しているという状況をつくっています。かつ、真っ黒に塗った花がその中に紛れていて、さらに視覚を錯綜させています。仕組みそのものは意外と簡単なのですが、効果と言えるところまで行き着くのに苦労しました。また照明を元に戻しますので、十分に味わっていただきたいと思います。
もともとは、光を打ち消すことだけを考えていたのですが、最後に伊藤さんがプログラミングをしてくださって、時折、部分的に何灯かをゆっくり消したりつけたりするということをしています。そうすると消したところが、床がこのように黒いがゆえに、異常に暗く見えるような状況になるのです。私はそれが非常におもしろいなと思って見ていました。
真壁
最後に伊藤さん、いかがですか。
伊藤
種明かしすると非常に簡単ですね。ただ、そのあかりで、あれだけ変わったシーンがつくれるのだということを皆さんにわかっていただければありがたいです。
事務局
乾さん、伊藤さん、真壁さん、どうもありがとうございました。(拍手)
-終了-